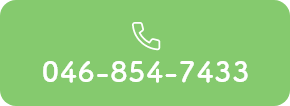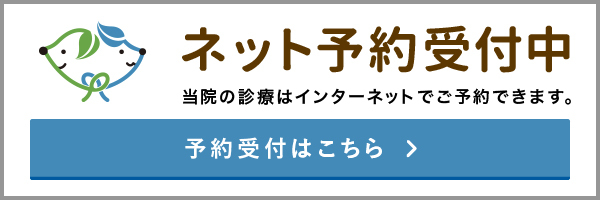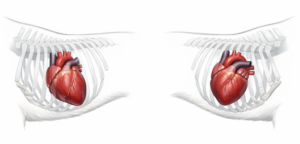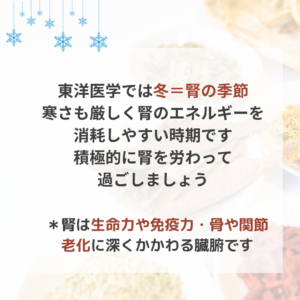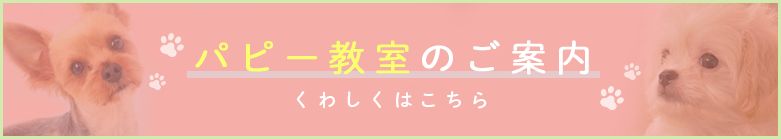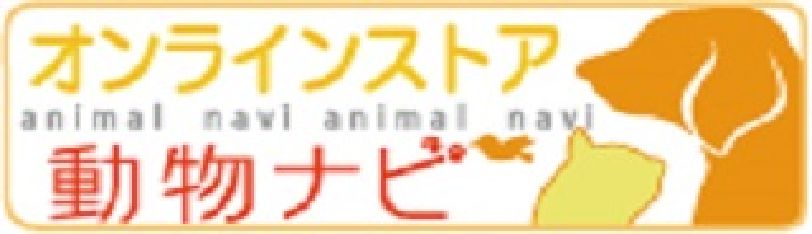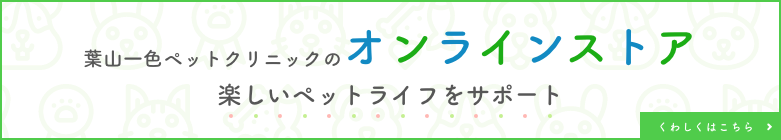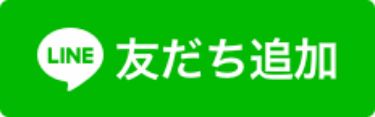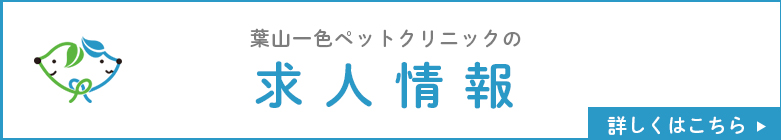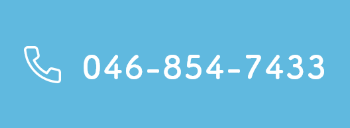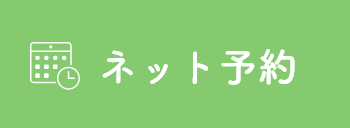皮膚科セミナーに参加してきました
先日、皮膚科専門医の先生のセミナーに参加してきました。 暑さも厳しくなってきた今の時期は皮膚病がとても多くなります。 今回は色々とある皮膚病の中でも特に多い「マラセチア皮膚炎」「食物アレルギー」「猫の皮膚病」についてのセミナーでした。 シャンプーの仕方から始まり、お薬の使い方や、食事の変更などについて最新の情報を色々と聞くことができました。 食物アレルギーの時の話ですが、こんな話が。 湘南のサーファーは納豆アレルギーが多いって知ってますか? クラゲと大豆はアレルギー物質に交差性があるため、クラゲに刺されると大豆アレルギーになることがあるからだそうです。 ちなみに、ダニと牛肉にも交差性があるみたいで、ダニに刺されると牛肉アレルギーになることもあるそうです。 この話を聞いて、ダニには気を付けようと心に誓いました。 アトピー性皮膚炎や食物アレルギーなどは生涯つきあっていかないといけないため、適切な管理が必要です。 皮膚でお悩みの事がありましたら是非一度ご相談ください。 葉山一色ペットクリニック 院長
2019.07.29
早期の慢性腎臓病ってなに?どうするの?
先日開催された、早期の慢性腎臓病のセミナーに参加してきました。 久しぶりのセミナーだったので、とても刺激を受けました。 うちの子も腎臓病の治療中なので、すぐに実践できることがあったのでさっそく試したいと思います。 今までも腎臓病の早期発見のために画像検査は行っていましたが、より一層画像検査の重要性を確認できました。 慢性腎臓病は残念ながら治すことが出来ない病気のため、早期に発見もしくはリスクを把握することがとても重要です。 症状が出る前に出来ることはたくさんあるので、定期的に腎臓病のリスクが無いか検診することをオススメします。 葉山一色ペットクリニック 院長
2019.07.22
2019.7.18 3周年を迎えました
\3周年を迎えました!!!/ これからも気軽に立ち寄っていただけるような 地域に寄り添った病院を目指してスタッフ一同頑張ります \これからもよろしくお願い致します/ \3が反対だった~version/ 空き時間に色々写真を撮ってみました お昼休みにケーキも食べました しゃもじは見るだけね
2019.07.20
車酔いについて
車酔いについて 乗り物の動揺のため 前庭の耳石器官または半規管受容体が刺激にさらされた動物に生じた状態で、動揺病ともいいます。 臨床症状として、生あくびや流涎、嚥下、嘔吐、血圧低下など。個体差が大きく、詳しい機序は不明です 満腹および過度な空腹状態は嘔吐を誘発しやすいので避けるようにしましょう。 乗り物酔いを経験した動物は乗り物に乗ること自体に不快感や緊張を感じて涎を出すことが多いです。 酔い止めのお薬や、車に慣れるトレーニング法もあるので お気軽に御相談ください
2019.07.08
2019.6.2 診察室トレーニング
診察室トレーニング パピー教室では 毎回診察室トレーニングを行っています 動物病院では、病気の治療や処置などをするため、ワンちゃんにとって苦手な場所であることも少なくありません 子犬(パピー)の頃から病院で楽しい経験をし、スタッフと良い関係を築いておくと 今後必要な処置もリラックスした状態で行うことができるようになります \お爪切りだって気にならないよ~/ 同時に飼い主さんにとっても、病院がワンちゃんにとって楽しい場所であれば受診しやすい環境となり、病気の早期発見・早期治療にもつながります \お口のチェックもへっちゃら/
2019.06.02
2019.5.31 夏のリース
病院の待合室に 夏バージョン のリースを飾りました 毎回 逗子のお花屋さん ダンデライオンさんに 素敵な季節のリースをお願いしています。今回は葉山の夏をイメージ アジサイ、オリーブに 貝や流木を散りばめて 素敵なリースを作って頂きました 一気に夏っぽいですね。 是非ご覧下さい
2019.05.31
2019.5.23 歯磨き教室
歯みがき教室 MIXのコテツちゃん \頑張るよ~/ お家で指磨きをしているコテツちゃんは 歯ブラシに慣れる練習からスタート 犬歯に軽くブラシをあてて→すぐにご褒美 を繰り返しました。 最初から無理強いしてしまうと 更に歯磨きが嫌いになってしまうので ステップを踏んで徐々にならしていきましょう ワンちゃんは 3日で歯垢が歯石になるので 間隔を空けすぎずに歯磨きしましょう ( 理想は毎日です ) しゃもじもお手本を見せてくれました☺️ コテツちゃん とってもお利口に頑張りました❗ちょっとずつ 歯ブラシに慣れていこうね
2019.05.25
2019.5.23 雷恐怖症について
雷や嵐、花火に恐怖を感じて行動に変化があるワンちゃんは多く、相談を受ける事も多くあります。 不安・恐怖が重度になると パニックになって怪我をしてしまったり、破壊行動など危険を伴います多くは時間の経過とともに悪化します。 動物病院では過剰な不安をおこしてしまう原因として 他のメディカルな問題があるか鑑別をしてから 問題行動の対応・治療を行います。 治療方法は 不安障害の度合いによって変わりますが ・薬物療法 ・行動修正法 を行います。 きちんと行動修正& 必要に応じて薬物療法を行うことで 8割程度のワンちゃんに改善がみられると報告があります 雷や花火のシーズン前に 治療をスタートする事が大切なので お早めに御相談ください
2019.05.23
2019.5.20 歯磨き教室
本日の歯みがき教室 トイプードルの希ちゃん 歯ブラシに対して嫌悪感がある希ちゃんは お口を触る練習からスタート (マズルコントロール ) 美味しい歯磨きペーストを指に塗って 軽く歯に触る所から始めました。(しゃもじがお手本になりました) 最初から無理強いしてしまうと 更に歯磨きが嫌いになってしまうので ステップを踏んで徐々にならしていきましょう ワンちゃんは 3日で歯垢が歯石になるので 間隔を空けすぎずに歯磨きしましょうね 歯みがき成功のコツは. ・ステップを踏んで無理矢理はダメ~!! ・ご褒美はしっかり、 たくさん褒めてあげましょう
2019.05.20
2019.5.10 歯磨き教室
本日の歯みがき教室 トイプードルのシェリちゃん 9ヶ月齢のシェリちゃん。 パピー教室でマズルコントロールをしっかり練習してくれているので 指を使った指磨き & 歯ブラシを使った磨き方のお話、実践練習をしました 歯垢が光るライトで今のお口の状態をチェック バニラ味の歯磨きペーストを使って指磨きもとても上手に出来ました 最初に無理強いすると歯ブラシを嫌いになってしまうので ちょっとずつ、そしてたくさん褒めてあげましょう ワンちゃんは 3日で歯垢が歯石になるので 間隔を空けすぎずに歯磨きしましょう(理想は毎日です) 歯みがき成功のコツは ・ステップを踏んで、無理矢理はダメ~ ・ご褒美はしっかりたくさん褒めてあげましょう!
2019.05.10
- HOME
- 病院ブログ (Page 15)
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
2026年 (11)
2025年 (52)
2024年 (58)
2023年 (28)
2022年 (29)
2021年 (36)
2020年 (59)
2019年 (98)
2018年 (45)
2017年 (1)