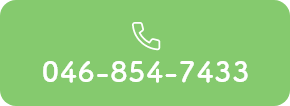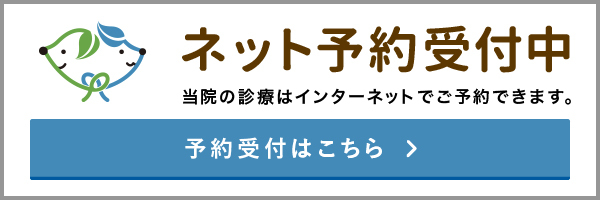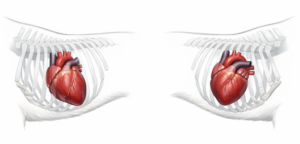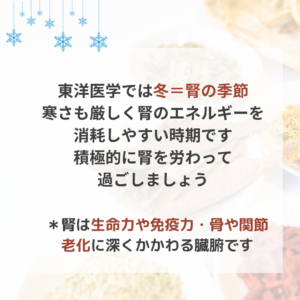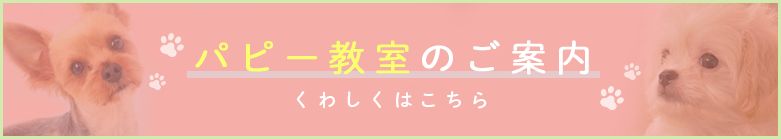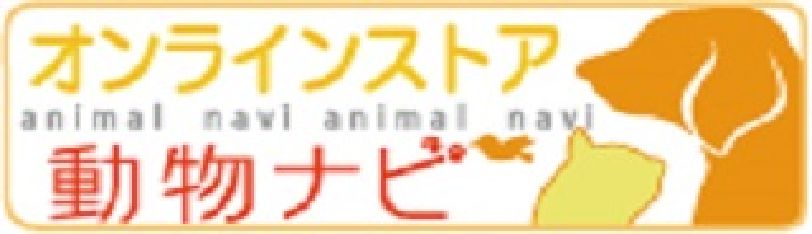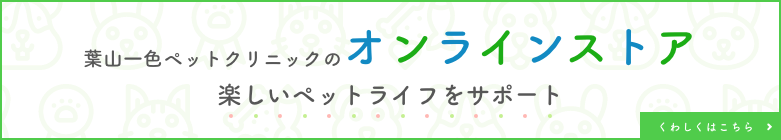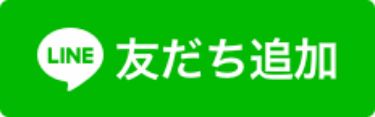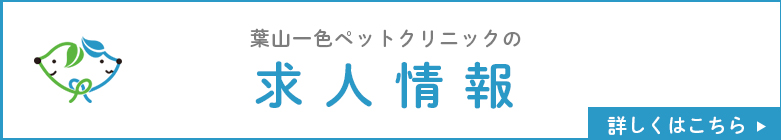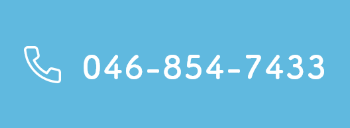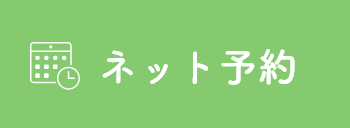5/26からの診療時間について
緊急事態宣言の解除に伴い 明日5/26から診療時間を通常通りに戻します 月〜土曜日 9:00〜12:00 15:00〜19:00 日曜祝日 9:00〜13:00 予防や健康診断キャンペーン期間のため お待たせすることが多くなっております ソーシャルディスタンス保持のご協力を宜しくお願い致します。
2020.05.25
駐車場が出来ました
\ 駐車場出来ました/ 病院の隣が駐車場になりました 3台駐車可能です (病院の前に3台、裏の駐車場にも1台駐車スペースがあります) 看板を設置して、しゃもじ&ムーとパチリ
2020.05.08
ハリネズミの病気(子宮腫瘍・黄疸)
先日、遠方よりいらしていただいたハリネズミさん。 まだ2歳にならない子ですが、子宮が腫れており、その他にも尻尾に腫瘤ができていました。 そのままお預かりさせていただき、翌日すぐに卵巣・子宮摘出を行わせていただき、尻尾の腫瘤も同時に摘出。 術後も食欲もバッチリでした。 病理検査の結果は、どちらも悪性腫瘍、、、。 ハリネズミさんは若齢でも腫瘍が多いです。 女の子で血尿が出ていたら、若い子でも要注意です。 こちらは別のハリネズミさん。 アルビノの子なので全体的に白い子なのですが、よくよく見ると鼻や口の中も白いです。 加えて耳の皮膚がなんとなく黄色みがかってます。 貧血と肝臓の病気(黄疸)を疑って血液検査を実施しました。 この子は大人しい子なので麻酔をかけることなく採血出来ました。 ハリネズミさんは検査するにも麻酔が必要になる事が多く、検査するのにもリスクを伴います。 結果は、貧血と肝不全が起こっていました。 点滴とお薬による治療で経過観察していきます。 ハリネズミさんをみさせていただく機会が多くなってきましたが、まだまだ力不足を感じます。 エキゾチックペットは症状をなかなか表に出さないため、おうちでの観察が重要です。 少しでも様子に異変を感じたら動物病院を受診することをオススメします。 「そんなことで病院に来ないでよ、、。」なんて思わないのでご安心を。
2020.05.05
2020.5.3 診療時間の変更について
緊急事態宣言の延長に伴い診療時間の変更もこのまま継続致します スタッフの出勤時間の調節、夜間帯の外出を控えるための処置となりますのでご理解ご協力をお願い致します 月〜土曜日 9:30〜12:00 15:00〜18:00 日曜祝日 9:30〜13:00 急な変更のため獣医師は通常の診療時間通りに待機はしておりますが、緊急のみの対応になりますのでご協力お願い致します
2020.05.04
2020.4.15 代行に行ってきました
休診日の本日は葉山町、逗子市、横須賀市の狂犬病予防接種の登録代行に息子と行ってきました (代行は月に1度まとめて行いますので済票や鑑札をお渡しするのに少しお時間をいただきます) \横須賀市は動物愛護センターに行ったよ/ 葉山町役場前の花の木公園のツツジは満開でした 狂犬病予防接種は体調の良い午前中の接種をオススメします (接種と一緒に健康診断&フィラリア検査も出来ます)
2020.04.15
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について
新型コロナウイルス感染拡大の収束が見通せない中、不安な日々をお過ごしのことと思います これからの狂犬病ワクチン接種等、予防シーズンにおける 待合室の混雑緩和のため 受付をして頂き診察の順番までの時間は お車または屋外にてお待ち頂く事をお勧めしています (受付の際、順番がきたら携帯電話への呼び出し、車種を教えて頂きお車へ呼びに行く‥‥etcご指定して頂ければと思います) 待合室での感染拡大防止にご協力をお願いいたします 早くこれまで通りに安心して暮らせるようになりますように
2020.04.02
2020.2.4 モコモコBIRTHDAY
我が家のアイドル モコモコが 2/4で16歳を迎えることが出来ました (しゃもじも2/4がお誕生日) 3年前から腎臓の数値が悪くなり 何度も体調を崩していましたが 持ち前の食欲と生命力で 体重もキープしてのんび〜り暮らしています \目線は遠く‥‥‥/ これからもQOL(生活の質)をなるべく落とさず 最期までのんびり苦しまず過ごしていけるように全力で見守っていきたいです。 ワンちゃんネコちゃんの慢性腎臓病は早期発見、そして食事療法がとても大切です。 血液検査とともに尿検査も重要なので シニア世代のワンちゃんネコちゃんは定期的な健康診断をオススメします
2020.02.05
うさぎの結石症
うさぎさんは、ワンちゃんネコちゃんと違い、オシッコの中にカルシウムが多く排泄されます。 そのため正常なオシッコでも結晶が見られることが多いため、尿検査を定期的に行っていても診断的な意義はあまり高くはありません。 うさぎさんで重要なのは、頻尿、尿漏れ、血尿などの症状やレントゲンやエコー検査などの画像検査になります。 先日、血尿を主訴に来院したウサギさんのレントゲン写真です 膀胱内に1cm程度の石があるのが確認できました。 うさぎさんの結石は食事療法では溶解しないため、手術が必要になります。 この子も手術を行うことになりましたが、さらなる結石症の予防の為に低カルシウム系のペレットに変更するなど食事療法も行うことになりました。 手術当日のレントゲンです 膀胱内にあった結石が消失しています。 この子は女の子であったため尿道が太く、運が良く自然に排出されていました。 通常1cmほどの大きさになると自然排出は難しいのですが、中には自然に排出されることも有ります。 ただし、大きさによっては尿道を詰まらせてしまったりすることもあるため、経過観察には注意が必要です。 結石を予防するためには低カルシウム系のペレットや牧草(チモシーなどのイネ科)に切り替え、適正体重を守ることが重要です。 うさぎさんは途中から食事の種類を変更することが難しいと言われていますので、食事の変更の際には根気よく徐々に行うことをオススメします。 院長 奈須俊介
2020.01.28
膀胱結石 ~寒い時期は要注意~
冬場は膀胱炎などの泌尿器系の病気のリスクが高くなる時期と言われています。 なぜだかご存知でしょうか? いくつか理由は有りますが、寒いと運動量が低下しそれに伴って飲水量も低下し尿が濃くなることにより結石症のリスクが高まる事や、排尿を我慢することによって結果として尿が濃くなること等が原因として挙げられています。 先日参加した腎臓病のセミナーでは、大学病院に来院した腎臓病の子のうちの約40%が尿石症などの泌尿器系の疾患を起こしたことがある子だと言っていました。 泌尿器系の病気の予防することは将来的な腎臓病の予防にもつながるため、定期的な尿検査などの健康診断を行うように心がけましょう。 先日膀胱結石の手術を行った子のレントゲン写真です この子は頻回尿、食欲不振、嘔吐、発熱などの症状も出ていました。 レントゲンで確認すると膀胱の中に大きな結石が2つあることが確認できます。 つづいてエコー写真です 黒くうつっているのがオシッコで、白く三角形にうつっているのが膀胱の中にある結石です。 エコーでは残念ながらいくつ石があるかは分かりませんが、レントゲンでうつらない結石もあるためエコー検査は必須です。 結石にはいくつも種類がありますが、出来やすい結石は「ストルバイト結石」と「シュウ酸カルシウム結石」の二つです。 「ストルバイト結石」は食事療法により溶解することができる結石なのですが、大きさや数や本人の状態により手術を選択する場合もあります。 「シュウ酸カルシウム結石」は残念ながら食事療法では溶解することが出来ないため、手術が適応になります。 この子は尿検査などから「ストルバイト結石」が疑われましたが、強い症状が出ていたため手術を行うことになりました。 摘出した結石 大きいもので1cm程度の結石がたくさん膀胱の中にあり、膀胱の粘膜に食い込んでなかなか取れないものもありました。 摘出後は膀胱や尿道内を洗浄し、結石の取り残しがないかを確認して手術終了です。 膀胱結石の大変なところは、再発することが多いところです。 結石の出来やすい要因はいくつかありますが、体質や性別などの変えることが出来ないものも要因の一つになってきます。 そのため、食事療法や飲水量の確保などを行いつつ尿検査や画像検査を行っていくことが重要になります。 以前尿石症になった事がある子で、しばらく検査を行っていない子は定期的に検査を行うことをオススメします。 院長 奈須俊介
2020.01.28
ハムスターの手術(眼球摘出・口腔内腫瘤摘出)
先日、ハムスターさんの手術を行いました。 どちらもジャンガリアンハムスターという40gほどの大きさの子です。 この子は口の中にできものが出来てしまったため、摘出を行った子です。 ほおっておくと噛んで出血をするリスクもありますし、邪魔してご飯が食べられなくなることもなります。 この子は腫瘤が口から出てきていたためすぐに発見できましたが、口の中に隠れてて見つからない子もいます。 ご飯を食べにくそうにしていたり、ずっとお口を動かして気にしている場合は注意が必要です。 この子は眼球が潰れてしまったため、摘出を行った子です。 はっきりとした原因は分かりませんが、外傷や感染などにより眼球ろう(眼球が小さくなってします状態)を引き起こしたものと思われます。 眼窩の内容物を摘出し眼瞼の縫合を行いました。 眼球ろうの子は多くは有りませんが、結膜炎などの目の病気はとても多いです。 ハムスターさんは綿や床材などに潜ることが好きなため、床材の素材によっては眼に傷をつけてしまうことも多いです。 ワンちゃんやネコちゃんと違い小さな変化に気が付きにくい子たちなので、よく観察していただき気になる事があれば早めにご相談ください。 院長 奈須俊介
2020.01.28
- HOME
- 病院ブログ (Page 13)
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
2026年 (11)
2025年 (52)
2024年 (58)
2023年 (28)
2022年 (29)
2021年 (36)
2020年 (59)
2019年 (98)
2018年 (45)
2017年 (1)